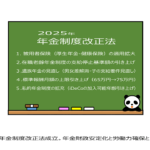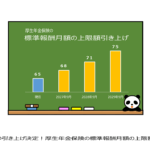年々厳しさを増す日本の夏。真夏日、猛暑日、そして、熱帯夜。
企業にとって常態化する暑い夏の喫緊の課題といえば、労働者の熱中症対策です。
近年、職場における熱中症による死傷者数は増加傾向にあります。
特に建設業や製造業、警備業、農業といった屋外作業や高温環境下での作業を伴う業種では、そのリスクは顕著です。
熱中症は、重症化すると意識障害や臓器不全を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。
労働者が健康を害することは、企業にとっても生産性の低下や社会的信用の失墜に繋がりかねません。
2025年6月1日からは、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症の重篤化を防止するための企業の措置がこれまで以上に明確化され、実質的に「義務化」されました。
これまでの労働安全衛生規則においても、熱中症予防のための努力義務は存在しましたが、具体的な措置内容が曖昧であったり、企業の認識不足が課題として指摘されていました。
今回の改正は、これらの課題を克服し、より実効性のある熱中症対策を企業に求めるものです。
今回は、2025年6月1日施行の企業の熱中症対策義務化の内容について、確認します。
1.真夏日に猛暑日に熱帯夜。その違いは。
夏の暑さを表す気象用語として、私たちがよく耳にするのが「真夏日」「猛暑日」「熱帯夜」です。
これらの言葉は、単に暑さを表現するだけでなく、熱中症のリスクを考える上で重要な指標となります。
・真夏日:日中の最高気温が30℃以上の日を指します。
まだ比較的過ごしやすいと感じるかもしれませんが、屋外での活動や運動をする際には、水分補給など基本的な熱中症対策が必要です。
・猛暑日:日中の最高気温が35℃以上の日を指します。
このレベルになると、熱中症のリスクは格段に高まります。屋外での作業はもちろんのこと、室内でもエアコンを使用するなど、積極的な暑さ対策が不可欠です。体温調節機能が追いつかなくなり、重篤な症状を引き起こす可能性が高まります。
・熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上の夜を指します。
日中の暑さが夜まで続き、気温が下がらないため、十分な休息が取れず、体が熱を冷ませない状態になります。睡眠の質の低下は、翌日の熱中症リスクを高める要因となります。特に、エアコンをつけずに就寝したり、通気性の悪い寝具を使用したりすると、さらに危険性が増します。
これら真夏日、猛暑日、熱帯夜の増加は、日本の夏の過酷さを象徴しており、労働者の熱中症リスクが年々高まっていることを示しています。こうした背景を踏まえ、今回の法改正は、企業がより積極的かつ具体的な熱中症対策を講じることを求めるものとなりました。
2.改正労働安全衛生規則の主なポイント
今回の改正で、企業に求められる熱中症対策はより具体的かつ包括的になりました。
主なポイントは以下の通りです。
2-1.WBGT値(暑さ指数)の活用と作業中止基準の明確化
WBGT値は、気温、湿度、輻射熱(日差しや地面からの照り返しなど)を総合的に評価する指標で、熱中症のリスクを客観的に判断するために最も有効とされています。
今回の改正では、WBGT値の測定を推奨するとともに、WBGT値が一定の基準を超えた場合には、作業の中止や休憩時間の延長、作業時間の短縮などの措置を講じることが明確に示されました。
これにより、個人の主観に頼らず、科学的なデータに基づいて作業の可否を判断することが求められます。
2-2.作業環境管理の徹底
作業場所の温度や湿度を下げるための対策(空調設備の設置、送風機の活用、遮光対策など)がより一層求められます。
屋外作業においては、日陰の確保やミストシャワーの設置なども有効です。
また、屋根付きの休憩所の設置や、作業場所とは異なる涼しい休憩場所の確保も重要となります。
2-3.作業管理の実施
作業時間や休憩時間の適切な設定はもとより、作業内容に応じた作業量の調整、熱への順化期間の設定(暑さに慣れるまでの期間に徐々に作業強度を上げる)、そして作業中の水分・塩分補給の徹底などが求められます。
特に水分補給については、のどの渇きを感じる前に意識的に摂取するよう指導することが重要です。
2-4.健康管理の強化
労働者の健康状態の把握は、熱中症予防の基本です。
定期的な健康診断に加え、体調不良を訴える労働者への配慮、持病を持つ労働者への個別指導、そして救急体制の整備(緊急時の連絡体制、応急処置ができる人員の配置、医療機関との連携など)が求められます。
特に、高齢者や持病を持つ労働者は熱中症のリスクが高いことを認識し、個別の対策を検討する必要があります。
2-5.労働者への教育と周知
熱中症の症状、予防法、対処法について、全ての労働者への周知徹底が義務付けられます。
定期的な研修会の開催や、ポスター、リーフレットの掲示などを通じて、労働者自身の熱中症予防意識を高めることが重要です。
また、初期症状を見逃さないよう、相互に注意し合う職場環境づくりも不可欠です。
(参照)
🔎 熱中症予防のための情報・資料サイト|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku
最後にまとめ。
企業における熱中症対策については、以下の3つの基本的な考え方が重要。
・「見つける」
WBGT値測定や労働者の体調変化を早期に把握し、熱中症リスクを予兆の段階で見つけることが重要。
・「判断する」
気象状況やWBGT値、作業内容、労働者の健康状態などから、作業の継続可否や必要な措置を適切に判断することが重要。
・「対処する」
休憩・水分補給、作業負荷軽減、涼しい場所への移動、医療機関への連絡など、状況に応じた迅速かつ適切に対処することが重要。
以上
supported by tantosya-masao