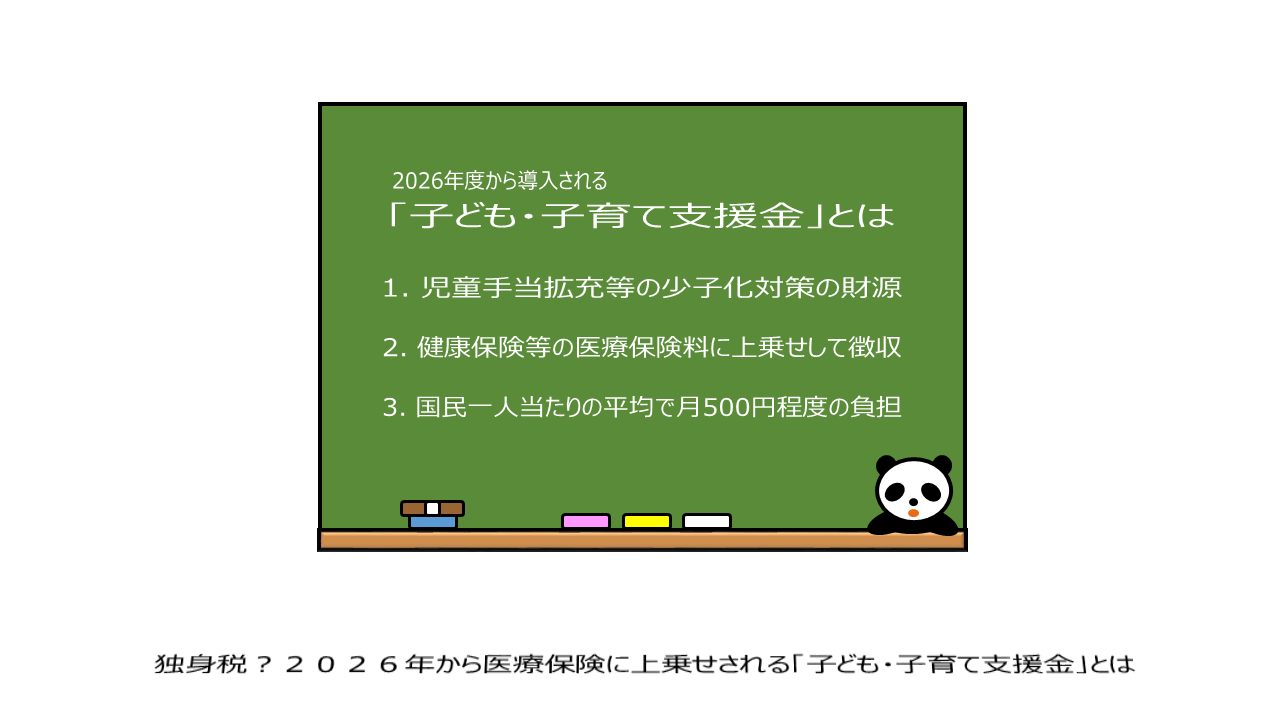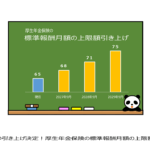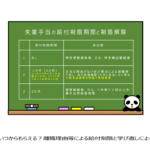2024年6月12日に成立した「改正子ども・子育て支援法」により、2026年度から導入が決定された制度が「子ども・子育て支援金」制度です。
制度導入の目的は、少子化対策のための財源確保。
支援金は、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。
医療保険料に上乗せされるため、子どもがいない人や子育てが終わった人も、徴収されます。
子どもの有無にかかわらず徴収されることから、一部では、「独身税」ともよばれています。
今回は、2026年度から導入される「子ども・子育て支援金」について、9つの質問で制度の仕組みや現在の少子化の課題等を確認します。
◆1.子ども・子育て支援金制度とは?
子ども・子育て支援金とは、少子化対策の財源として2026年度から新たに導入される制度です。
支援金は医療保険料への上乗せにより徴収され、児童手当の抜本的拡充等、子ども・子育て支援策に充てられます。
医療保険の保険者である全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団は、被保険者から徴収した支援金を、子ども・子育て支援納付金として納付する義務を負うこととなります(子ども・子育て支援法第71条の3第2項)。
なお、支援金制度は2026年から2028年にかけて段階的に実施されますが、給付については2026年度までに集中的に取り組みされ、給付先行型での対応となります。
◆2.一部で独身税とよばれる理由は?
社会保険料は本来、加入者が保険料を拠出し、将来的にその保険給付を受けるという「負担と給付の牽連性」が明確であるべきだと考えられています。
牽連性とは、関係性やつながりという意味。
しかし、子ども・子育て支援金は、医療保険料に上乗せされる形で一律徴収されるにもかかわらず、その給付対象は「子ども・子育て支援」に限定されます。
つまり、子どもがいない人や子育てを終えた人も、医療保険料を支払うことで支援金を負担することになりますが、その負担に見合う直接的な「給付」を受ける機会は基本的にありません。
この点が、「独身税」とよばれる理由の一つです。
世代間の公平性や、社会保険の原則である負担と給付の明確な結びつきという観点から、制度設計の不透明性や不公平感が指摘されています。
政府は「全世代型社会保障」の観点から理解を求めていますが、国民からは具体的な給付が見えにくいという不満が上がっています。
◆3.医療保険料上乗せによるメリット・デメリットは?
メリットは、既存の徴収システムを利用するため、新たな徴収制度を構築する手間やコストが少ない点が挙げられます。また、税金ではなく保険料として徴収されるため、財源の安定性が高いとされています。
デメリットは、医療保険料が実質的に値上がりするため、国民の家計負担が増加することが挙げられます。また、医療保険料の内訳が複雑になり、国民にとって負担額や使途が分かりにくくなることが挙げられます。
なお、制度設計としては、介護保険と同様に、支援金は医療保険料と区分して管理されます。
具体的には、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定と労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、2025年度より「子ども・子育て支援特別会計」(こども金庫)が設置されます。
◆4.個人が負担する金額は?
政府の試算では、国民一人あたり月平均は、2026年度は250円、2027年度は350円、2029年度は450円程度です。
ただし、これは平均値であり、所得や加入している医療保険の種類によって実際の負担額は異なります。
◆5.支援金の使い道は?
支援金が充てられる事業は、法律で以下の①~⑦と定められています(子ども・子育て支援法第71条の3第1項)。
① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)…2024年10月から
② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)…2025年4月から制度化
③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)…2026年4月から給付化
④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))…2025年4月から
⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)…2025年4月から
⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 …2026年10月から
⑦ 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する2028年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金
児童手当の所得制限の撤廃など、支援策はすでに開始されています。
◆6.子ども・子育て支援の財政規模は?
年3.6兆円規模です。
そのうち、子ども・子育て支援金は、2026年度6千億円、2027年度8千億円、2028年度1兆円が負担の目安額です。
◆7.子ども一人あたりの給付額の上乗せは?
子ども一人当たり平均の給付の上乗せ額は、高校生年代までの合計で約146万円です。
内訳としては、児童手当の拡充で106万円、妊婦のための支援給付で10万円、こども誰でも通園制度で14万円、共働き・共育ての支援で17万円です(106+10+14+17≒約146万円)。
なお、現行の平均的な児童手当額約206万円とあわせると、18歳までの一人当たり累積給付額の合計は約352万円となります。
◆8.少子化の現状は?
日本の出生数は、2000年代に入って、急速に減少しています。
2022年生まれの出生数は77万759人で、これは統計開始の1899年以来、最低の数字です。
現在、日本の総人口は1億2千5百万人ですが、現状のまま少子化が進展すると、2050年代に1億人、2060年代には9千万人を割り、2070年には8千7百万人程度となります。
今後、わずか50年で、人口の3分の1を失うおそれがあります。
◆9.こども未来戦略の加速化プランとは?
現状のまま少子化が進展すると、2030年代には、若年人口は現在の倍速で急減することとなります。
政府は、2030年代に入るまでに少子化傾向を反転させるため、今後3年間の集中的な少子化対策として、「加速化プラン」を策定しています。
そして、その「加速化プラン」の財源確保策の一つが、子ども・子育て支援金制度です。
最後にまとめ。
・子ども・子育て支援金は、少子化対策の「こども・子育て支援加速化プラン」の財源となる。
・子ども・子育て支援金は、子どもの有無にかかわらず、医療保険料に上乗せして徴収される。
・現状のまま少子化が進展すると、日本は今後わずか50年で人口の3分の1を失うおそれがある。
(参照)
🔎 子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
🔎 こども未来戦略会議|内閣官房ホームページhttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/index.html
以上
written by soudanin-hajime