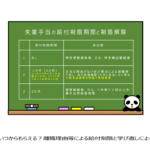政府は、リスキリング(学び直し)を推進しています。
遡ること2022年10月3日。
当時の岸田首相は所信表明演説で、リスキリング支援として5年間で1兆円もの「人への投資」を表明しました。
その政策の一つが、2025年10月よりスタートする「教育訓練休暇給付金制度」です。
制度の中身は、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合、離職時の基本手当に相当する給付額が国から支給される制度となっています。
一言でいうと、「無給で学び直しをした場合は経済的支援として国がお金を支給します。」という制度です。
今回は、教育訓練休暇給付金制度の内容について、9つのポイントに絞って、わかりやすく解説します。
1.教育訓練休暇給付金制度とはどのような制度ですか?
教育訓練休暇給付金制度は、労働者が自らのキャリア形成のために教育訓練を受ける目的で、会社の就業規則等で定めた無給の教育訓練休暇を取得した場合に、その期間中の生活支援のための給付金が国から支給される制度です。
これにより、経済的な不安なくスキルアップに専念できる環境を整え、労働者のリスキリングによるキャリア形成を促進することを目的としています。
2.制度はいつから開始されますか?
2025年10月1日から制度が開始されます。
3.どのような人が給付金の対象となりますか?
在籍中の雇用保険の一般被保険者が、以下の①・②を満たす場合に対象となります。
①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。
被保険者期間としてカウントされるのは「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」又は「賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月」です。
②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。
但し、過去に失業給付(基本手当)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。
なお、離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算可能です(前述の失業給付等を受給していた場合は通算不可)。
4.どのような休暇が給付金の対象となりますか?
以下の①~③を満たす休暇の取得が給付金の支給対象となります。
①就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること。
②労働者本人が教育訓練を受講するため自発的(※)に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること。
※事業主の提出書類により申請者が解雇等の予定がないことを確認。虚偽申告は罰則の対象。
③職業に関する教育訓練を受けるための休暇であること。
具体的には、以下のいずれかに該当するものが対象。
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
5.給付金はいくら支給されますか?また支給期間はどのくらいですか?
支給額(給付額)と支給期間(給付日数)は以下の通りです。
◆支給額(給付額)
離職した場合に支給される基本手当(いわゆる失業手当)と同額が支給されます。
給付日額は、失業給付の算定方法と同様、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定した賃金日額から算出されます。
厚生労働省の「教育訓練休暇給付金のご案内」のパンフレットで示されている額面月収に応じた概算の給付額は、以下の通りです。
| 額面月収 | 給付月額 |
|---|---|
| 25万円 | 約17万円 |
| 35万円 | 約19万5千円 |
| 45万円 | 約22万5千円 |
◆支給期間(給付日数)
給付を受けることのできる期間は、休暇開始日から起算して1年間となり、教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上教育訓練を受けられない場合は最大4年間)。
所定給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて、90日、120日、150日のいずれかとなります。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
支給期間(受給期間)と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合も、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができます。
6.給付金を受け取るための申請手続きはどのように行いますか?
申請手続きは、ハローワークを通じて行います。
事業主が手続主体となる場合は事業所の所在地を管轄するハローワーク、労働者が手続主体となる場合は労働者の住居所を管轄するハローワークへ申請手続きを行います。
具体的な流れとしては、以下の厚生労働省のパンフレット記載の流れを参照ください。

7.給付金を受けるにあたって労働者側の注意事項はありますか?
教育訓練休暇給付金の受給により、被保険者期間がリセットされるため、原則として、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく給付金を受給できなくなります。
8.給付金を受けるにあたって事業主側の注意事項はありますか?
解雇等を予定している労働者について虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となります。また、教育訓練休暇を取得した労働者を解雇等すると、一定期間、雇用関係助成金の支給を受けられなくなる場合があります。
9.制度の利用にあたって事業主側にメリットはありますか?
事業主側としては、以下のようなメリットが期待されます。
・従業員のスキルアップと生産性向上
従業員が経済的な不安なく長期的な教育訓練に取り組めるため、企業が求める専門性の高いスキルや知識を習得しやすくなります。その結果、従業員一人ひとりの生産性や業務効率が向上し、ひいては企業全体の競争力強化につながります。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)やグローバル化に対応するためのリスキリング(学び直し)を従業員が主体的に進めることが可能になります。
・優秀な人材の確保と定着率向上
教育訓練休暇制度が充実していることは、「従業員の成長を支援する企業」として魅力的な企業イメージを形成し、採用活動において他社との差別化を図ることができます。特に、自身のキャリア形成に意欲的な若手人材にとって、長期的な学びの機会が提供される企業は大きな魅力となります。スキルアップした従業員が、より責任のある役職に就くなど、社内でのキャリアパスが明確になることで、転職への動機を減らし、人材の流出防止にもつながります。
・従業員エンゲージメントとモチベーションの向上
従業員の主体的なキャリア形成を支援する姿勢を示すことで、従業員の企業に対する信頼感や愛着(エンゲージメント)が高まります。従業員が自ら学びたい分野に挑戦できる環境があることで、仕事に対するモチベーションや意欲が向上します。
最後にまとめ。
・教育訓練休暇給付金とは、労働者がリスキリングのために、会社の就業規則等で定めた無給の教育訓練休暇を30日以上取得した場合に、国から生活費支援として給付金が支給される制度である。
・休暇開始前に雇用保険被保険者期間が5年以上ある在籍中の雇用保険の一般被保険者であれば、離職時の基本手当(いわゆる失業手当)と同額が、雇用保険加入期間に応じ90日・120日・150日のいずれかの期間について支給される。
・労働者にとっては無給の休暇中も国から給付金が支給されるため経済的な不安を軽減しキャリア形成に必要なスキルや知識を習得できるメリットがある。事業主にとっては従業員のスキル向上による生産性の向上や優秀な人材の確保・定着率の向上や従業員エンゲージメント・モチベーションの向上が期待できる。
以上
written by soudanin-hajime