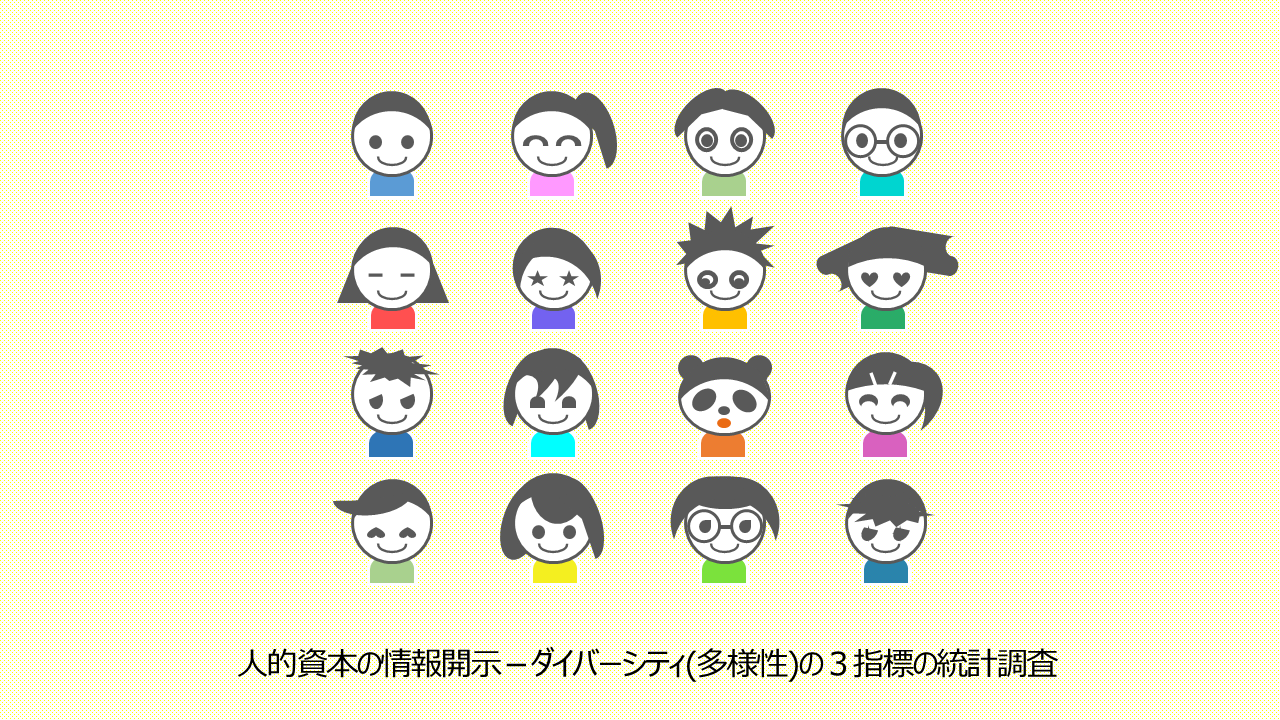政府は、2022年8月30日に人的資本可視化指針 を策定し、公表しています。
人的資本可視化指針では、19の開示事項が例示されました。
また、2023年3月期の有価証券報告書からは、上場企業に人的資本の情報開示が義務づけられる予定です。
人的資本の開示事項の一つに、「ダイバーシティ(多様性)」の指標があります。
有価証券報告書では、「従業員の状況」欄へ記載されることとなります。
今回は、人的資本開示項目の一つである「ダイバーシティ(多様性)」の代表的な3指標について、参考となる統計調査を紹介します。
1.女性管理職比率
「女性管理職比率」の統計調査は、厚生労働省の雇用均等基本調査を参照しましょう。
管理職といえば、課長以上が一般的ですので、課長以上の「女性管理職比率」の推移を確認します。
↓ クリックして拡大 ↓
令和3年度の課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は、12.3%となっています。
平成27年度以降、女性管理職比率は12%程度で推移しています。
ざっくり、管理職の中で、10人に1人は女性管理職といえるでしょう。
自社の女性管理職比率の算出にあたっては、はじめに、基準日と管理職とする役職を決定しましょう。
女性管理職比率は、女性管理職数を分子に、総管理職数を分母として、算出します。
2.男性育休取得率
「男性育休取得率」の統計調査も、厚生労働省の雇用均等基本調査を参照しましょう。
↓ クリックして拡大 ↓
令和3年度の調査では、男性育児休業取得率は18.9%となっています。
平成27年度の4.4%から、ここ数年で取得率は大きく伸長しました。
ざっくり、配偶者が出産した男性の、5人に1人は育児休業を取得しているといえるでしょう。
自社の男性育児休業取得率の算出にあたっては、はじめに、対象期間を決定しましょう。
自社の会計年度でもよいですし、雇用均等基本調査と同様に、10月1日から9月30日とすることでもよいでしょう。
男性育児休業取得率は、対象期間に育児休業を取得した男性数を分子とし、対象期間に配偶者が出産した男性数を分母とすることで、算出します。
3.男女間賃金格差
「男女間賃金格差」の統計調査としては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査を参照しましょう。
対象となるのは一般労働者(短時間労働者を除く常用労働者)となります。
対象となる「賃金」は、6月分の所定内給与額の平均です。
↓ クリックして拡大 ↓
令和3年度の調査では、男性の賃金を100とした場合の女性の賃金は、75.2です。
平成27年度以降、おおむね、75の水準で推移しています。
女性の賃金は、男性の賃金の4分の3が、現状です。
また、女性活躍推進法が改正され、常用労働者301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」の公表が必須項目となりました。
令和4年7月8日に施行され、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとなります。
女性活躍推進法による「男女の賃金の差異」は、男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合です。
平均年間賃金は、1事業年度の賃金総額を、同年度の労働者数で除して、男女別に算出します。
算出方法の詳細は、以下の資料を参照しましょう。
🔎 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について【PDF】|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
以上
written by suchika-hakaru