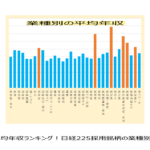会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者として年金制度に加入しています。
厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和4年度)によると、第3号被保険者は721万人。
内訳としては、男性12万人、女性709万人で、女性の割合が98%です。
共働き世帯は約7割に達し、男女共同参画社会の実現に向けて法制化も行われていますが、国民年金第3号被保険者の加入状況からは、多くの女性が夫に扶養されている現況がわかります。
収入の稼ぎ手である夫が死亡した場合に備える公的年金制度が遺族年金です。
子のある妻に支給される遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類。
厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業年報(令和2年度)によると、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している妻の平均年金月額は13.2万円です。
今回は、夫(国民年金第2号被保険者)に扶養されていた子のある妻(国民年金第3号被保険者の子のある妻)に支給される遺族年金の支給額について、確認します。
1.遺族基礎年金の支給額
配偶者に対する遺族基礎年金は、子のある配偶者にのみ支給される母子(父子)年金です。
子とは、18歳になった年度の3月31日までの子、又は、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子をさします。
遺族基礎年金の支給額は、795,000円(令和5年度)です。
上記の額に子の加算額として、1人目及び2人目の子の加算額は各228,700円、3人目以降の子の加算額は各76,200円となります。
例えば、子が1人の場合の遺族基礎年金の支給額は、795,000円+228,700円=1,023,700円となります。
月額では、約8万円となります。
🔎 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
🔎遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-01.html
2.遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金は、主たる稼得の担い手であった厚生年金被保険者等が死亡した場合、遺族に従前の生活を保障することを目的として支給されます。
支給額は、死亡した配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、以下のA+Bの合計額です。
A:平成15年3月以前の加入期間
「平均標準報酬月額×0.7125%×平成15年3月までの加入期間の月数」
B:平成15年4月以降の加入期間
「平均標準報酬額×0.5481%×平成15年4月以降の加入期間の月数」
🔎 報酬比例部分|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html
計算式に用いる用語の補足等は省略し、2つの事例により、具体的な老齢厚生年金の報酬比例部分の額の確認方法を紹介します。
2-1.夫の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)以上の場合
日本年金機構の「ねんきんネット」で、夫の老齢厚生年金の額を確認しましょう。
🔎 ねんきんネット|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
「ねんきんネットの年金見込額」>「これまでの加入実績に応じた年金見込額の情報」の「老齢厚生年金額」が、遺族厚生年金の計算に使用される基礎額となります。
これまでの加入実績に応じた夫の老齢厚生年金額の4分の3の額が、遺族厚生年金の支給額です。
2-2.夫の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合
被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算することとなります。
老齢厚生年金を算出するための計算式は「平成15年3月まで」と「平成15年4月以降」で異なります。
平成15年は2003年ですので、投稿日時点の2024年において300月に満たないということは、おおむね、「平成15年4月以降」の計算式を用いることで差し支えないでしょう。
平成15年4月以降の加入期間に使用する老齢厚生年金の計算式は、「平均標準報酬額×0.5481%×平成15年4月以降の加入期間の月数」です。
月単位の考え方を年単位の考え方にし、0.5481%を0.55%にまるめることで、ざっくりとした老齢厚生年金の額を求めることができます。
…ざっくりとした老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算式…
「平均年収(円)×0.55%×加入年数」
例えば、亡くなった夫の平均年収が600万円、被保険者期間25年とすると、6,000,000円×0.55%×25年=825,000円となります。
825,000円に4分の3(0.75)を乗じた額である618,750円が遺族厚生年金の額となります。
月額では、約5万円となります。
🔎 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
なお、40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻については、子どもが成長し遺族基礎年金が受給できなくなった場合、中高齢寡婦加算を受けることが可能です。
中高齢寡婦加算の額は、年額596,300円です。
🔎 遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html
3.子のある妻の遺族年金の試算表
「1.遺族基礎年金」と「2.遺族厚生年金」で例示した場合の試算例を試算表にあてはめました。
…試算の前提…
・夫の死亡当時、妻は国民年金第3号被保険者。
・18歳未満の子が1人。
・夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額は825,000円。
・令和5年度の試算。

試算例では、遺族年金の額は約160万円、月額では約13万円の結果となりました。
なお、遺族年金は非課税となりますので、支給額=受取額となります。
🔎 遺族の方に支給される公的年金等|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
最後にまとめ。
・子のある妻は、夫が死亡すると遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できる。
・遺族基礎年金は、子どもの数が増えれば増えるほど、年金額が増える。
・遺族厚生年金は、亡くなった夫の収入が高ければ高いほど、また、年金加入期間が長ければ長いほど、年金額が増える。
以上
written by sharoshi-tsutomu